
関西国際空港
沈下のしくみ ~沈下発生のメカニズム~
沈下が起きるしくみ
粘土は、意外と水をたくさん含んでいて、柔らかい沖積粘土(沖積層の粘土)であれば体積の7割が水で、固い洪積粘土(洪積層の粘土)でも4割程度の水を含んでいます。埋め立てた土の重さによって、海底の粘土に含まれている水が絞り出されることによって沈下が生じます。例えて言うと、水を含んだスポンジを上から押さえると、押し出された水の体積分だけスポンジの体積が減ります。これと同じメカニズムで、空港島の重さによって押し出された水の体積分だけ海底の粘土の体積が減り、これが沈下という現象となって現れます。スポンジの水はすぐに押し出されますが、粘土は水を通しにくいので、何十年、何百年といった長い時間をかけて沈下が起きます。この現象を土質学の分野では「圧密(アツミツ)」と呼んでいます。沈下が進み、粘土に含まれている水が徐々に押し出されるにつれて、粘土はどんどん固くなり、粘土が島の重さを支えられるまで固くなると沈下は止まります。
また、海底地盤だけでなく、埋め立てに使った土砂自体も自らの重さで圧縮するので、空港島の地表では、海底の沈下量に、この埋立土砂自体の圧縮も加えた量が沈下となって現れます。

【粘土が沈下するしくみ】
空港島はとても重い
粘土は、何十万年というオーダーの長い時間、地中にあると、セメントのように徐々に固くなります。洪積層は古くて、かなり固くなっているため、従来のように海岸沿いを埋め立てたぐらいの重さでは、たいして沈下しません。しかし、空港島は水深の深い沖合を埋め立てたために埋立土砂も多く必要で重く、ある程度の深さまでの洪積層では、上から載った島の重さが粘土の固さを越えてしまい、沈下が生じるであろうことが、すでに事前の調査段階から想定されていました。詳しくは、『空港島の重さと沈下』のグラフをご覧下さい。
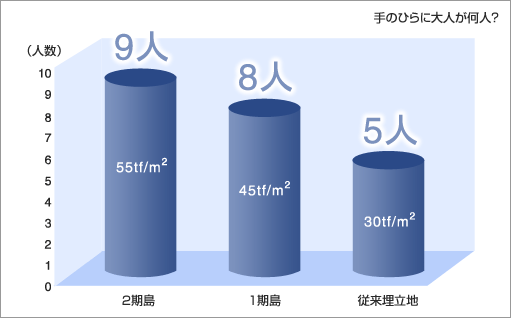
【埋立地の重さ比べ】
空港島の重さと沈下
これは、海底地盤のボーリング調査により採取した粘土についての試験を行った結果をグラフにしたものです。
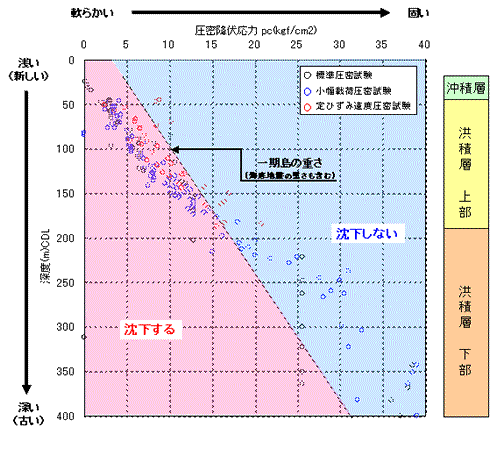
<図の見方>
- グラフは、地盤の深さと強さ(圧密降伏応力)との関係を図化したものです。
- 空港島の埋立土砂の重さと、海底地盤の重さを合わせた重さがグラフの直線(1期島の重さ)です。
- 深くなるにつれて海底地盤の重さが加わるので、全体の重さも増えていきます。
- 直線より右側に点がある場合は、この重さに耐えられる強さがある、つまり”沈下しない”と考えられます。
 集中豪雨対策
集中豪雨対策 集中豪雨対策
集中豪雨対策 神戸空港を利用されるお客様へ
神戸空港を利用されるお客様へ